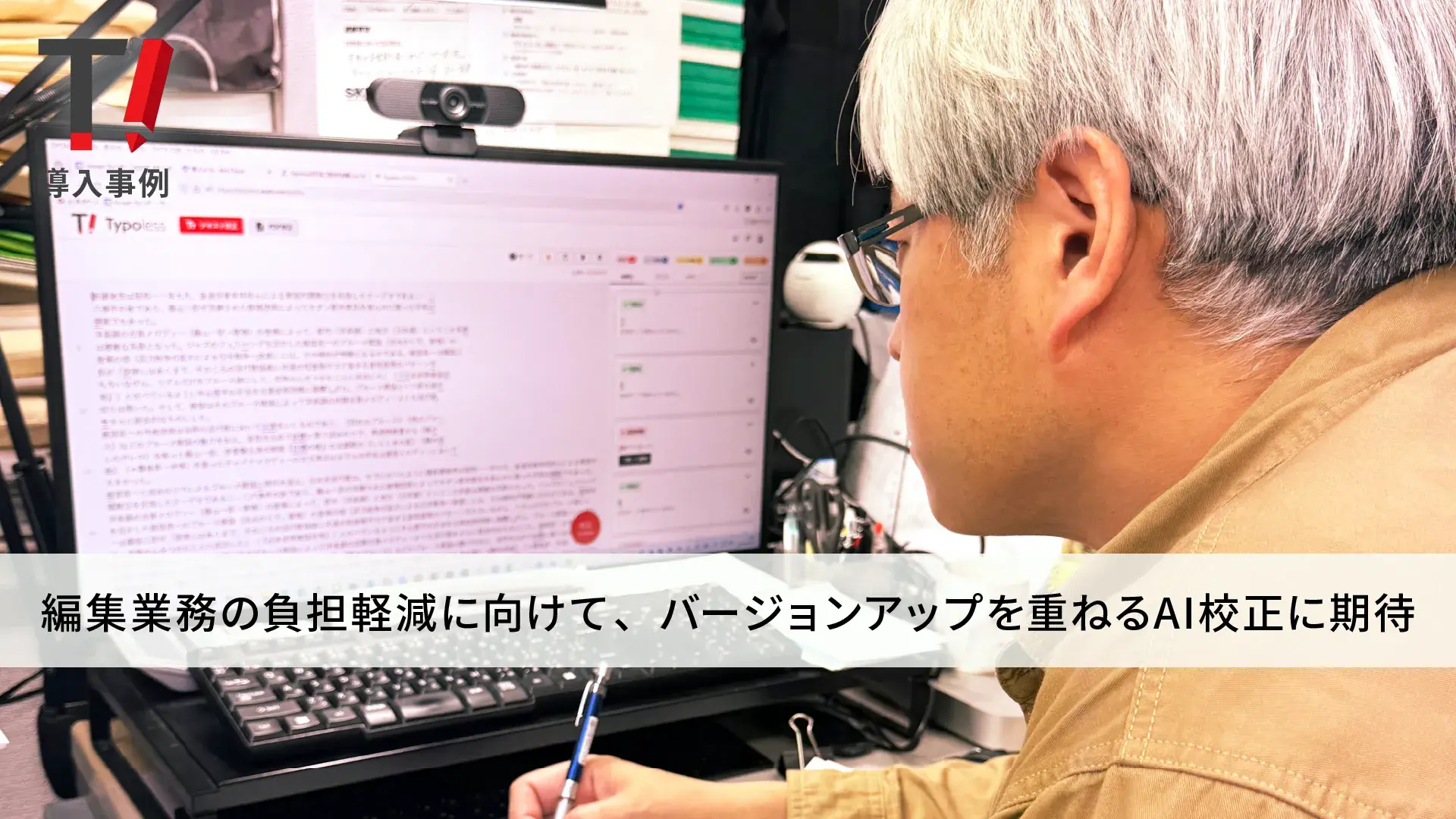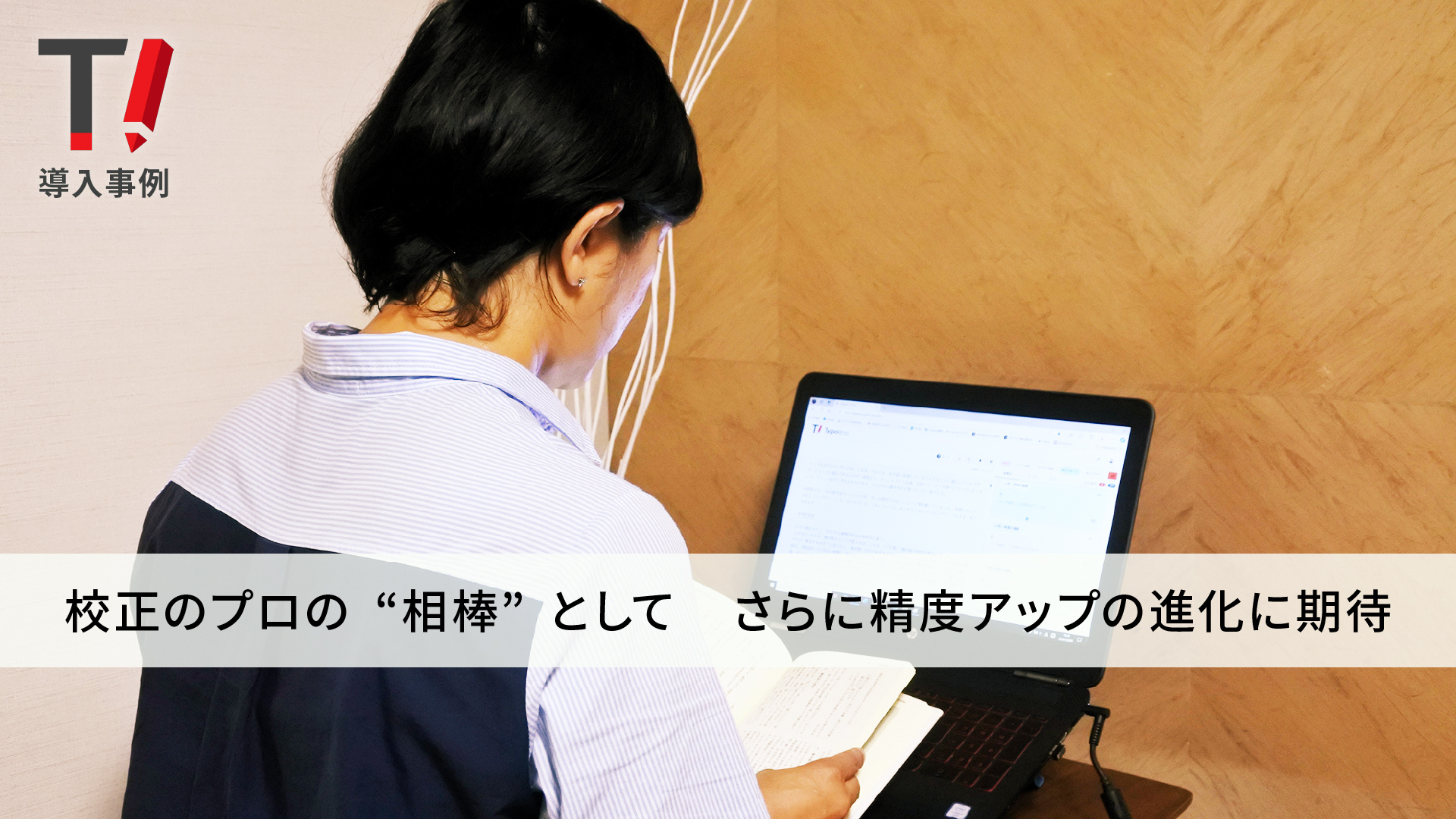人が気づきにくい校正を指摘し、自社とパートナーの信頼性向上に貢献
株式会社シスパック 代表取締役
黒田 壽祐 様
(ご利用プラン:スタンダード)
Webサービスやシステムコンサルティングを手掛ける「シスパック」の社長である黒田壽祐様は、ソニーに在籍した26年間で、パソコンや光ディスクの事業に携わった経歴の持ち主。69歳になった現在も一人で会社を経営し、社外から送られてきたテキストを発信前にチェックする立場にある。サービスや企業の信頼性を保つために、2024年3月から文章校正AI「Typoless」の導入を決めた。今回、黒田社長に「Typoless」導入の経緯や活用方法、そして導入後の変化について詳しくお話しいただきました。
- ご利用者はエンジニア出身の経営者
- 1万字以上のメルマガ配信にも活用
- ビジネスパートナーからも感謝の声
メルマガのサービスや公的機関への文書に利用
 株式会社シスパック 代表取締役 黒田 壽祐 様
株式会社シスパック 代表取締役 黒田 壽祐 様
シスパックでは現在、私が一人で業務を担当してパートナーの企業とさまざまなプロジェクトを進めています。そのため、事業に直接関わる場面で、文章をお客様などに提出する機会が多くあります。
Typolessを利用する頻度が多い業務は主に2つあり、1つは当社が配信を請け負っている会員制メールマガジンの校正です。著名な自動車評論家によるメルマガでファンも多く、1本当たり1万から1万5千字ほどの記事を月に数本配信しています。
もう1つは、公的機関から入札などで業務を受託した際、提出する報告書などの校正にTypolessを使うことにしました。求められる文書の数と量が多く、また内容と共に文章のクオリティーにも十分に注意を払う必要があります。
一方でメルマガは筆者の個性が大事ですから、くだけた表現などに対してはTypolessの指摘を反映せずに、元の表現をそのまま生かす場面も多くあります。文章の種類による使い分けを、今後も心がけていくつもりです。
ご活用ポイント①
AI校正の精度は、ご利用される文章に応じて「積極的」から「消極的」までの3段階に切り替えることが可能です。

画面では気づかない「へ」と「ヘ」の違い
校正ツールを探そうと思ったのは、メルマガの配信後に筆者から訂正の依頼が何回かあったのがきっかけです。Webのバックナンバーは修正が可能ですが、配信してしまったメールは取り返しがつきません。配信する前に私も誤字脱字などのチェックをしていましたが、人の目ではやはり限界があるため、しっかりと校正できるツールはないかと調べ、Typolessにたどり着きました。

実際に使うに当たっては、他のツールと比較検討しました。Typolessを選ぶ決め手となったのは、「AI学習」と呼ばれる機械学習の積み重ねです。過去40年分の朝日新聞の記事データを学習しているということで、信頼できると感じました。無料トライアル期間中も特に問題なく使えて、今まで気づかなかった校正の指摘がかなりあったので、正式に使い続けることになりました。
利用して約3カ月経ち、発信する文章のクオリティーは確実に向上していると思います。定量的な比較は難しいのですが、誤字などを正しく判断できるため、メルマガの筆者の方も喜んでおられました。当社の取引先から官庁に提出する書面に関しても、文章のクオリティーが上がることは信頼関係に直接結びつきますので、非常に感謝されています。
今まであった修正の指摘は、「行程」と「工程」の間違いや、「超える」と「越える」のどちらを選ぶか。ひらがなの「へ」とカタカナの「ヘ」の違いは、画面を見ただけでは全く気づかないと思います。
 「行程」と「工程」、「超える」と「越える」、ひらがなの「へ」とカタカナの「ヘ」への指摘例
「行程」と「工程」、「超える」と「越える」、ひらがなの「へ」とカタカナの「ヘ」への指摘例
エンジニアの業務にも活用の余地
Typolessを利用して気づいたのは、1つの文章に対してかなりの数の指摘があることです。その中には、本当に直さなければいけない箇所と、あくまでも指摘であって修正の必要のない箇所があります。
人によってはそれを余計なお世話と感じるかもしれませんが、漏れがあるよりはいいと私は思っています。気づかなかったようなミスの可能性を、どんどん指摘してもらったほうがありがたいです。
ご活用ポイント②
校正の指摘を表示したくない場合は「無視する」のボタンを押すことで、その文書で同様の指摘を見えなくできます。さらに、「永続的に無視する」を選ぶと、他の文書を校正しても同じ指摘を無視します(アカウント設定から戻すことが可能)。※プレミアム以上のプラン、ならびにエンタープライズ契約限定の機能

要望としては、校正を指摘している該当箇所をもう少し見やすくしてもらえると、もっと使いやすくなると思います。その辺りは、世に出てまだ間もないサービスということで、今後のバージョンアップにも期待しています。

私自身はソフトウェアエンジニアとしてキャリアを歩み始めて以来、キーボードでの入力は約50年の経験がありますが、文章を校正する能力に関して自信があるわけではありません。他の方から誤解されるような表現や印象にならないように、Typolessを活用しています。
若いエンジニアの方々も、設計の仕様書や取扱説明書などで、大量の文章を扱う場面があると思います。そのときにこのような校正ツールがあることで、より安心して内容に集中できるのではないでしょうか。
(掲載内容は2024年7月時点の情報です。)