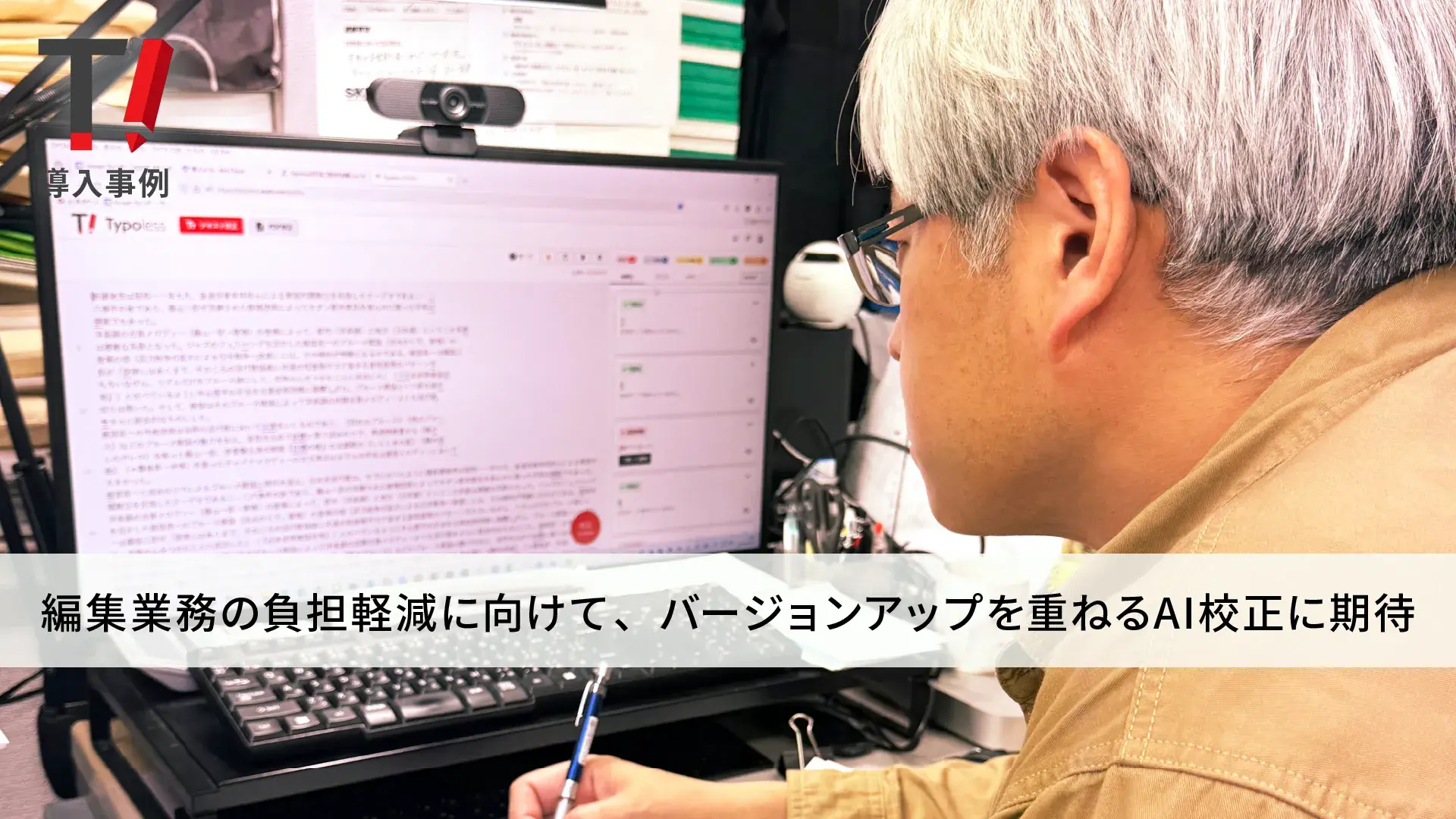校正のプロの“相棒”として さらに精度アップの進化に期待
編集・校正者
胡桃澤 いずみ 様
(ご利用プラン:プレミアム)
論文や書籍、ウェブなどの文章の校正を手掛ける胡桃澤いずみ様は、フリーランスの編集・校正者として10年目を迎える。以前からさまざまなデジタルの校正ツールを試し、文章校正AI「Typoless」は「良文サポート」機能が実装されたのを機に、プレミアムプランへとアップグレードした。「文章ならなんでも文章校正ツールを試す」スタンスで普段から利用している「Typoless」が、校正のプロから見てどこまで使えるツールなのか、率直な意見を語っていただいた。
- 使いやすさ重視のシンプルな画面デザイン
- 時間効率が上がり、仕事の受注増に直結
- 言葉を振り返るきっかけになり、注意力が高まった
ようやく登場した感のある、本格的に使える校正ツール
私に校正をご依頼される法人のお客さまは、スタートアップ企業や印刷サービス会社、広告会社などです。個人では研究者や医師、コンサルタントが中心で、校正の作業範囲や深度、期待値などもお客さまによって異なります。分野は私自身の経験が長い金融や金融システムが中心ですが、教育や言語などアカデミックなものから芸術まで、多岐にわたります。
 編集・校正者 胡桃澤 いずみ 様
編集・校正者 胡桃澤 いずみ 様
現在は校正の約1割は手書きで、パンフレットなどの印刷物に昔ながらの校正記号を使って作業しています。残りの約9割は文字がデータで送られてくるので、 Typolessで処理できます。1カ月に扱うのは30万字程度。ほかにも、自分で書くブログや、ネットで気になった文章などにTypolessをかけて、ツールの性能やクセを把握しています。
2024年4月にTypolessを導入する以前は、校正の約80%を自分だけで作業し、残りの20%は校正ツールを使ったり、アウトソーシングしたりしていました。有料や無料の校正ツールは3、4年前から試してきて、Typolessに出会い、ようやく本格的に使えるものが出てきたと思いました。

これまでの校正作業の課題は、お客さまの校正の捉え方やローカルルールが多様で、ツールや人の手に頼っても、結局は自分の手作業になってしまうという点でした。私個人としても、疲れて集中力が切れてきたときのうっかりミスを見つけたいという気持ちがありました。
Typolessが良かったのは、使いやすさに尽きます。Web版の話ですが、ボタンの位置もわかりやすくて、これぐらいシンプルなほうがいいのかなと思いました。比較した他の有料サービスは、画面のデザインをがんばりすぎたのか、ごちゃごちゃして逆に使いにくくかったですね。

新聞記事のような表現を使った文章になるというのも、私やお客さまにとってアドバンテージになります。AI校正は朝日新聞の記事データを学習したもので、ルール辞書には新聞記者が使う校正ルールを登録していると聞いて納得しました。
「日本書紀」の指摘を機に、上のプランへと更新
実は、Typolessをしばらく使ったらやめるつもりでした。AI校正やルール辞書で校正の指摘はしてくれるのですが、私の仕事で活用するには、それだけではまだまだ不十分と感じていました。継続のきっかけは、ある日、「日本書紀」の「紀」が「記」になっている間違いを指摘してくれたことです。間違えようがない言葉なのですが、うっかり見過ごすところで、気づいてくれて良かった、助けられた、と胸をなでおろしました。
ちょうどその頃、プレミアム以上のプランに「良文サポート」機能が追加されたので、スタンダードからプレミアムに変更して契約を続けることを決めました。主語と述語をそろえるなど、文章全体をフォローするような作文補助機能が欲しいと以前から思っていて、その不満にある程度こたえてくれるものでした。良文サポートについては、将来的にもっと進化したものを開発してくれると期待しています。
ご活用ポイント①
「良文サポート」 ……文章をより美しく、読みやすくするためのサポート機能。助詞の連続や読点の多用など、18項目がチェック可能です。※プレミアム以上のプラン、ならびにエンタープライズ契約限定の機能
※プレミアム以上のプラン、ならびにエンタープライズ契約限定の機能

私のTypolessの利用法は、自分の目で校正する前に2回に分けて使っています。2回というのは、AI校正と良文サポートで全体を見て、カスタム辞書とルール辞書で細かいところを校正、と分けたほうが作業しやすいからです。4種類の校正をまとめて行うと指摘が多くなり、1種類の校正を4回だと時間がかかるので、2種類ずつ2回がちょうど良いと感じています。最後に炎上リスクも確認します。
手作業で校正するときも同様です。私は3回に分けて文章を見ることが多いのですが、それぞれ違う観点でチェックをすることで精度の高い校正ができ、作業の流れも明確になります。Typolessはその点、4種類の校正がそれぞれ色分けされて見やすいので、使う人によって校正の仕方も選択しやすいと思います。
カスタム辞書には、「して下さい」を「してください」とひらがな表記するなど、使う頻度の多いルールを登録しています。医療などの難しい専門用語は再び使う場面が少ないので、一般的によく使う言葉だけを選んでいます。
ご活用ポイント②
「カスタム辞書」 ……用語集やルールなど、ユーザー自身がキーワードを設定できます。CSVファイルでのインポート/エクスポートも可能で、エンタープライズプランでは3つの辞書がご利用いただけます。
※プレミアム以上のプラン、ならびにエンタープライズ契約限定の機能

デジタルでの正しい校正を発信していってほしい
Typolessを導入したメリットは、時間効率が上がり、校正ミスが減ったことです。その分だけ、仕事の受注にも結びついていると思います。人に頼む場合と比べて、やり取りや確認の時間が一瞬で済んでコストがかからないだけでなく、いつも均一のレベルの校正ができるのは大きなメリットです。
もちろん校正ツールとしてはまだ完璧なものではなく、最高到達点が100点とすれば、現在は60点ぐらいかなという感覚です。例えば、新聞社の校閲記者なら見逃さないであろう指摘はありませんし、ひどい文法で書かれた文章はまったく校正してくれません。もちろん、思い違い、記憶違いの言葉も推測してくれません。今後学習すべきデータはまだまだ多いと思います。私は、元新聞記者ですから、人間の作業のすごさを知っています。60点の評価は厳しいと思いますが、それでも他のツールに比べて優れているし、これから理想に向けて開発していきそうなので、さらに精度が高まっていくことを期待しています。
ここ1年ぐらいで、私が校正する元の文章は誤字脱字が減りつつあり、多くの方がひそかに校正ツールを使っているという印象があります。その一方、世の中ではデジタルの校正について、ルールのようなものはまだ定まっていません。実際にTypolessは紙の校正ルールが根底にあるように感じます。でも世の中はデジタルの校正ルールが望まれています。これが正しい校正ルールなんだ、という新しい標準を発信できるようなツールを、ぜひTypolessには目指していってほしいですね。
現時点でAI校正ツールは、私にとって相棒のような存在になっています。校正をツールだけで完結させたいという、100点でないと満足できない人には不満があるでしょう。しかし、相棒として使う分には非常に頼りになります。
また、校正に反映されずに余計と思われる指摘でも、言葉を振り返るきっかけになり、私自身も言葉への注意力が高まりました。一人で作業をしていると切磋琢磨(せっさたくま)する相手はいませんが、その時にTypolessが良き相棒になってくれるはずです。
(掲載内容は2024年7月時点の情報です。)