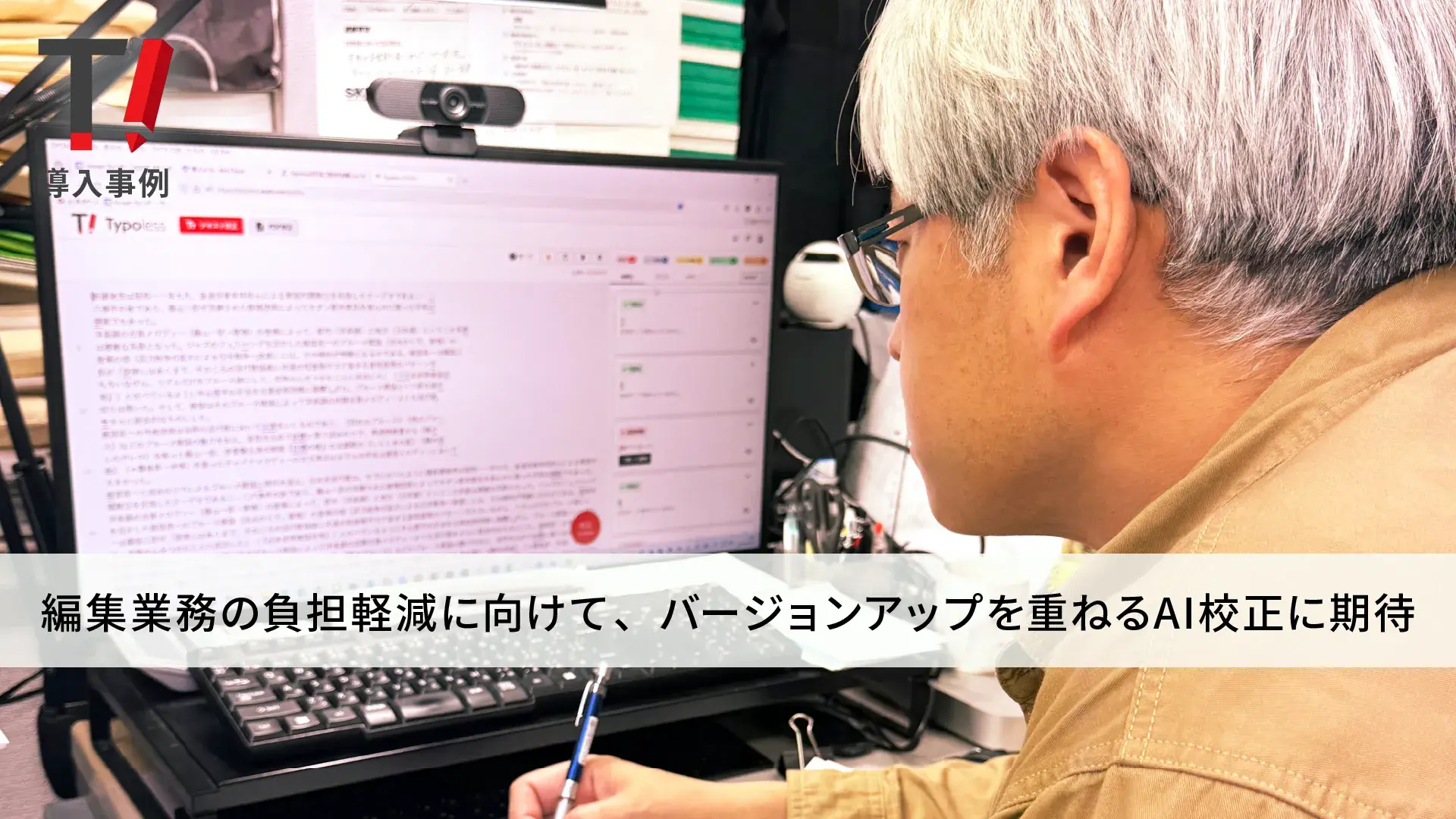Typoless 導入事例 | 業種:食料品
日本たばこ産業株式会社 様
表現チェックを効率化、本質的な内容の精査に注力

- 文章のクオリティーを上げるためのアドバイスも表示
- 新聞社のノウハウが詰まっており、プレスリリース向き
- 親切な日本語表示で、直感的に使えるインターフェース
「心の豊かさを、もっと。」をグループのパーパスに掲げ、たばこ・医薬・加工食品を中心に事業を展開している日本たばこ産業(JT)。主軸となるたばこ事業は、世界130以上の国と地域で製品を販売しており、国ごとに異なる文化や法規制に対応してきた。たばこという製品の特性上、社会に向けた情報発信には細心の注意を払う必要があり、高畑様が担当する広報業務においても例外ではない。社外に情報を届けるための日本語に求められるのは、文法的に正しいだけでなく、表現が適切で誤解を招かないこと。高畑様のチームがプレスリリースなどを制作する際に、文章校正AI「Typoless」をどう活用しているのかを聞いた。

適切かつ正確な情報開示に向けて、文章校正AIを導入
――JTは国内に類を見ない業種で、注目度も高い企業です。広報業務にはどんな特徴がありますか?
高畑友章 様(以下「高畑」) 情報を適切かつ正確に開示しなければならないことは、他社の方々と共通するところです。当社の広報ならではの特徴は2つあると考えています。1つは、グローバルに事業を展開していること。130以上の国と地域で商品を扱っており、世界中で起こる様々な事象がテーマとなります。
もう1つは、たばこという商品に対してさまざまな意見があるからこそ、一つひとつの表現により注意をしなければならない点です。誤解を招きかねない表現をしてしまえば、たばこを取り巻く多くの方々にご迷惑をおかけしてしまうリスクもあります。喫煙所整備などの分煙の取り組みについても、取り組みの目的や当社の考えを正確に表現しなくてはなりません。
――具体的にはどのような点に気を付けて情報発信していますか?
高畑 たとえば、新製品を発売する際には、その魅力は伝えながらも、未成年の方が過度に興味を持つような内容にならないように検討する必要があります。製品区分などの用語を正しく使用することも求められており、日本国内で一般的に「電子たばこ」と呼ばれるニコチンの入っていない商品と、我々が扱っている「加熱式たばこ」の定義は、明確に線引きをしています。
――「Typoless」のご利用状況を教えてください。
高畑 2024年10月末からエンタープライズプランを契約しています。広報部の中で、プレスリリースなどを作成するチームの3人と、有価証券報告書などの法的な開示文書を担当するチームの2人が使用しています。
――校正の業務フローにどんな変化がありましたか?
高畑 プレスリリースの場合、それぞれの案件を扱う部署と広報部の担当者が協議して文章のレビューを重ね、この内容で行こうと固まった段階でTypolessにかけ、指摘を受けた内容を反映するかを判断します。これまでは、担当者と広報部の他のメンバーによる「複眼チェック」という、シンプルな方法でした。
もちろん現在も、メンバーによる複眼チェックは引き続き行っています。ベースの部分はTypolessでしっかりとチェックしているため、我々は「てにをは」などを何度も細かく見る必要はなくなりました。その分、リリースの内容に集中できるようになったと思います。

単なる誤字脱字チェッカーでなく、文章の質を上げる指摘も
――「Typoless」を導入された経緯は?
高畑 社内の他部署から紹介してもらいました。無料トライアル期間があったため、みんなで試してみた結果、文章を校正する機会が多く、利用頻度が高い我々の部署で正式に導入することになりました。
――校正にどのような課題を感じていましたか?
高畑 まずは時間の問題が挙げられます。これまでの複眼チェックでは、文章を作成した本人は目を皿のようにして見ます。依頼されたメンバーも真剣に校正しますので、1点のプレスリリースを少なくとも20分、長い時には30~40分かけて確認していました。
さらに、誤字脱字ではなくても、同じ文書に「取り組み」と「取組」が混在するなど、細かい見逃しをしてしまうことがありました。その時は発表の直前に発見して、表記揺れを修正しました。幸いにも大きなトラブルは今まで起きていませんが、人の目によるチェックだけでは常に不安が残っていました。
――従来の校正方法では、デジタルツールを使っていましたか?
高畑 広報の関係者が使う校正リストを表計算ソフトにまとめ、アナログでのチェックに使用していました。デジタルでの校正という意味では、今までツールなどは使っていません。開示前の機密情報を扱っていますので、セキュリティーがとても重要です。Typolessはデータがサーバーに一切残らないため、信頼性が担保されており、導入の条件をクリアできたと言えます。
――「Typoless」の採用を決定したポイントは?
高畑 非常に手軽で、軽く動くという点です。文章をコピー&ペーストしてボタンをクリックすれば、数秒で校正結果が表示され、そのスピードは非常に魅力的でした。これがもし、ファイルを読み込んで時間がかかった場合、心地良く使うことはできなかったと思います。
校正の内容についても充実しており、単なる誤字脱字チェッカーではないと感じました。個人的にハッとさせられたのは、一文が長くなってしまった時に出る「良文サポート」機能の指摘です。我々は文を短く切って分かりやすくしているつもりなのですが、言いたいことが多いと、長文になってしまうケースも多々あります。生成AIでは、そこまで気の利いた指摘はしてくれないと思います。文章のクオリティーを上げるためのアドバイスまで表示されるのには驚きました。

文章をより良くするために、伴走してくれる「先生」
――「Typoless」の導入後は、どのような効果や気づきがありましたか?
高畑 校正にかかる時間は、大幅に短縮されたと感じています。気づかされたのが、書き手の癖は文章に意外にも出てしまうこと。よく読むと微妙な違和感がある表現に対して、Typolessを通してある程度安定したトーンの文章にすることで、一定のクオリティーを担保できるようになったと思います。特にプレスリリースは、情報をもっとも届けたい相手は報道機関になります。新聞社の長年のノウハウを蓄積したTypolessでチェックすることは、非常に合理的だと感じています。
――メンバーの皆さんはスムーズに使うことができましたか?
高畑 パソコンの日常操作の延長で使えることは大きかったです。インターフェースが直感的に使いやすく、校正の指摘も画面の右側に表示され、容易に理解できるようになっています。メニューや設定などの説明は日本語で分かりやすく、「使い方」のガイドを見ることはほとんどありませんでした。
――今後はどのように活用していきたいですか?
高畑 まずは、オフィシャルな文章のチェック以外にも、社内のちょっとしたメモやメールなどにも気軽に使っていきたいと思っています。
もう1つは、我々だけの話ではないのですが、社内の関係部署も校正サービスを使うようになれば、お互いの業務が効率化されるのではないかと考えています。現状では、我々が文章のレビューを依頼されて、それをTypolessにかけて修正したものを担当部署に戻す際に、なぜこのように修正したのかを細かく説明しています。そのためのやり取りに時間と手間を要するため、元の文章からTypolessでクオリティーが担保されていれば、お互いに不要なやり取りが減らせます。その分、表現ではなく文章の内容について精査でき、本質的な議論に時間を割けるようになると思います。
――「Typoless」はご自身の業務において、どのような存在ですか?
高畑 文章を添削してくれる、国語の先生ですね。単なるチェックのためのマシンというよりは、より良くするために伴走しながら問いかけをしてくれる存在だと思います。私自身もTypolessを使うようになって、書き始める段階から「一文が長くなっているから見直そう」などと意識するようになりました。今後も学ばせてもらうことはたくさんあると考えています。

日本たばこ産業株式会社(JT)
1898年に設置された大蔵省専売局をルーツに、日本専売公社を経て1985年に設立。グループの中核事業であるグローバルたばこ事業では、130以上の国と地域でたばこ製品を販売している。海外で積極的にM&Aを行い、販売数量は世界第3位(中国専売公社を除く)。87年に進出した医薬事業では、JTが新薬の研究開発を担い、グループ会社の鳥居薬品が製造・販売などを行う。加工食品事業は、冷食・常温事業のテーブルマーク、調味料の富士食品工業が中核を担っている。
【URL】
https://www.jti.co.jp/
【プレスリリース一覧(公式サイト内)】
https://www.jti.co.jp/investors/library/press_releases/index.html