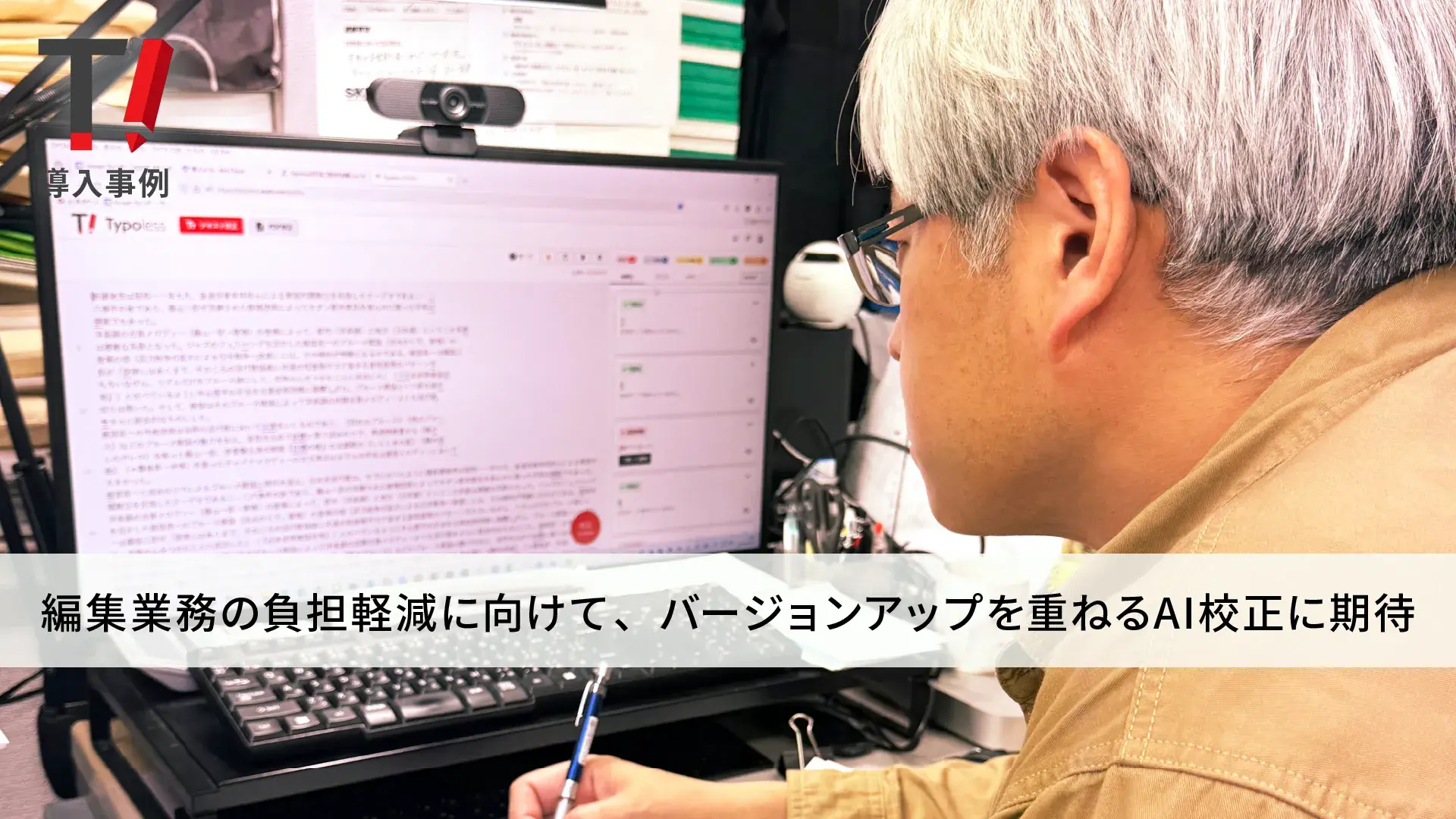Typoless 導入事例 | 業種:建設コンサルタント
八千代エンジニヤリング株式会社 様
機能が随時アップデート、常に最新の校正環境を

- サブスクで機能が更新される安心感。リモートワークにも適応
- 個人がスルーしていた部分まで校正し、より客観的にチェック
- 「良文サポート」機能で、自分の文章を見直すきっかけに
私たちの暮らしを支える社会インフラ整備において、事業計画から調査、設計、維持管理までを推進し、事業者・発注者の“ブレーン”の役割を果たすのが建設コンサルタントだ。八千代エンジニヤリングは、日本有数の総合建設コンサルタントとして世界約150の国と地域で実績を持ち、卓越した技術力で社会課題の解決に貢献してきた。社内外への広報活動においては、高い専門性と広い地域性を持つ情報をいかにコントロールして適切に発信するかが求められており、2024年5月に導入した文章校正AI「Typoless」は指針の一つとして業務を支えている。広報課の小林様に、お話を伺った。
行政の言葉や専門用語もわかりやすく伝えたい
――広報課ではどのような形で情報発信していますか?
小林史明 様(以下「小林」) 社内に関しては、12ページの社内報を毎月発行しています。またビジネス用コミュニケーションアプリを使って即時性のある情報を、社内に都度発信しています。社外に対しては、会社案内やサステナビリティレポート、採用向けの冊子などを発行しています。さらに社外向けのリリースは頻度が多く、週に1本以上のペースで発信しています。
――社外向けのリリースを拝見すると、ジャンルも多岐にわたる印象です。建設コンサルタントという業種の広報業務の特徴を教えてください。
小林 当社は、道路や鉄道や河川といった社会インフラの整備において、ゼネコンなどが行う「施工」以外の設計や維持管理などに携わっています。官公庁のお客様が多くを占めますが、民間企業向けにも幅広い業務を展開しています。社外向けのリリースは、行政の言葉や専門用語のままだと難しいため、かみ砕いてわかりやすく伝えることが課題であり、校正の果たす役割が大きくなります。
――広報担当者も幅広い知識が求められると思いますが、広報課は何人で業務を行っていますか?
小林 派遣社員を入れて6人の体制で、複数の業務を遂行しながら、毎日何かしらの文章を書き、何かしらの校正をしているという頻度で、それらの作業全てにTypolessを活用しています。
――「Typoless」の導入に至ったのは、やはり業務負担の軽減という理由が大きいのでしょうか?
小林 はい。1つの文章は少なくても必ず2人以上でチェックするようにしていましたので、極端な話、校正だけで1日が終わる日もありました。どこまで校正に時間がかかるのかは個人によって差もあり、何とかして改善できないのかという課題がありました。
業務効率と文章の質、両面において導入効果

――校正に関わるサービスを検討して、「Typoless」を採用された理由は?
小林 いろいろ検討する中で、買い切りの校正ソフトを使うという案もありました。しかし、世の中の情勢によって内容も変化しますので、その度に製品を再購入する必要が発生してしまいます。それに比べると、Typolessには「炎上リスクチェッカー」などの機能が随時更新されるという安心感があります。また当初はなかったのですが、WordやPDFの校正にも対応していく予定であると聞いたことも、導入したきっかけの一つになりました。
――サブスクのWebサービスだから、常に最新の状態で使えるというわけですね。リモート対応という意味でも、スムーズな導入につながったのではないでしょうか?
小林 それも非常に大きいですね。私の場合ですと、週1~2回ほどのリモートワークになります。これまでの校正作業では、新聞記者が使う用語集が課内に置いてあり、必要に応じてそれを確認しながら校正していました。Typolessがあれば、リモートワーク時に用語集を確認しなくても、気になるところを指摘してくれます。

――実際に「Typoless」を導入して、どのような効果がありましたか?
小林 作業時間などの定量的な面では、用語集などを使いながらアナログで校正する手間がかなり軽減できたと思います。Typolessを1回通しているので、みんなで確認するという時間も短縮できました。
文章の質に関して言えば、これまでは個人が気になったところは確認するものの、気にならないところはスルーしてしまっている側面がありました。Typolessは自分たちが気づかなかったところも含めて文章全体を校正してくれるので、文章のチェックが属人的でなくなり、より客観的になったと思います。
――「自分たちが気づかなかったところ」の校正は、どのようなものですか?
小林 たとえば、1つの文に「、」が多かったり表現が冗長だったりするのを指摘してくれるのは、非常にありがたいです。自分の文章を見直すきっかけにもなりますね。
社名は「ア」でなく「ヤ」、カスタム辞書にも登録

――業務では生成AIも活用されているそうですが、校正作業で使い分けしていますか?
小林 やはり朝日新聞の過去の記事などを学習したTypolessの校正には安心感があり、重宝しています。
――「カスタム辞書」には、どのような用語を登録されています?
小林 代表的なのは自社名です。「エンジニ」の後は「ア」ではなくて「ヤ」で、社内で間違える人はいませんが、カスタム辞書には登録しています。ほかにも、「部署」を社内では「部所」と表記していますが、社内向けと社外向けで使い分けています。
――PDFファイルの校正をお使いいただいているご感想をお聞かせください。
小林 PDFからテキストをコピーしてから校正する手間がなくなったのは良いと思います。当社の場合は紙の社内報を毎月発行しており、初校から4校ぐらいまではPDFでやり取りするので、その時には活用しています。また、メディアから取材を受けた際にも、取材後にPDFで原稿を確認するケースが少なくありませんので、広報担当としてもありがたいです。

――他の部署でも導入されたとお聞きしました。
小林 広報課で導入した2カ月後に、マーケティング課が「広報が使っているなら同じものを」という流れで導入しました。マーケティング課でも社外への情報発信に使用しています。
――企業内で「Typoless」の導入がもっと広がるには、何が必要だと思いますか?
小林 広報としては、様々な部署が自分たちで校正を行えるようになるのは非常に良いことだと思いますが、当然ながらそこにはコストが伴います。より多くの人数に合わせたリーズナブルな料金プランがあれば、業務内容にかかわらず企業内に広がっていく可能性があると思います。
八千代エンジニヤリング株式会社
1963年設立の総合建設コンサルタント。「千代に八千代に生き続け、未来永劫に渡って、人類社会のために貢献し発展してほしい」が社名の由来。道路・橋梁・河川・ダム・公園などの社会インフラを中心に技術・知的サービスを提供してきた。2021年から「サステナビリティ経営」を掲げ、さまざまな社会課題に対応し、千年先も豊かな社会を目指している。
【URL】
https://www.yachiyo-eng.co.jp/
【サステナビリティレポート(サイトよりダウンロード)】
https://www.yachiyo-eng.co.jp/sustainability/
【公式note】
https://note.yachiyo-eng.co.jp/